嗜好品文化研究会
平成24年度第1回研究会
「脳と嗜好品」 中西 重忠
| ゲスト講師●中西 重忠/なかにし しげただ●財団法人大阪バイオサイエンス研究所所長。1942年岐阜県生まれ。京都大学名誉教授。京都大学大学院医学研究科修了、米国国立衛生研究所客員研究員、京都大学医学部助教授から教授、大学院医学研究科および生命科学研究科教授、医学研究科科長・医学部長を経て退官。2005年より現職。1979年、沼正作京大教授とともに発見・発表した多ホルモン前駆体の構造・遺伝子・進化に関する研究で、朝日賞受賞。1991年“記憶のもと”と考えられるNMDA型グルタミン酸受容体の構造を世界で初めて解明した。1997年日本学士院賞・恩賜賞。2000年全米科学アカデミー外国人会員、2006年文化功労者。2009年日本学士院会員。 |
はじめに
茶、コーヒー、酒、タバコなどでリラックスしたり、元気が出てきたりするのは脳がどのようにはたらいているのか。好きな音楽を聴いたり、映画を見たりしても同じ効果があるが、脳のメカニズムは同じなのか。──あらかじめそんな質問をいただいている。
今日は最初に、「おいしいものを食べたい」という時の脳のメカニズムをお話ししよう。ところで、「好ましい」と感じ、「求める」ということは、お互いにもちろん繋がりはあるが、脳機能のメカニズムは実のところ少し違う。「好む」に関する脳の機能はまだ充分には分かっていない。一方、「求める」ことについては、ここ十年程の間に随分分かってきた。したがって、話の後半では、「求める」という脳のメカニズムを説明し、さらにそれは単に嗜好だけでなく、動物が生存していく上でどういう役割を担っているかについても議論したい。
味覚
我々が「味を感じる」というのは、まず舌の感覚器が働く。その感覚は5つから成り立っている。塩味、酸味、甘味、苦味、旨味である。口内に食物が入ると──実際さまざまな味がその食物には含まれているのだが── 舌の上の感覚器でそれぞれの味情報に分かれ、別々の回路で脳に伝わり、脳で最終的に統合されて、その食物の独特の味を感じている。さらに言えば、おいしさは味だけでなく、においや見た目の情報、つまり嗅覚、視覚なども含めたさまざまな情報が脳で統合された結果である。
[図1]は味覚器であり、舌の粘膜の上皮細胞層にある味蕾をさらに拡大したものである。中央の味細胞がそれぞれの味成分に反応し、その情報が神経節細胞へ伝えられて脳に伝わる。(神経節細胞から先が「神経」であり、その前の味細胞は感覚細胞である。ただし、その終末側で次の神経節細胞を興奮させるので、神経細胞の機能も持つ。)
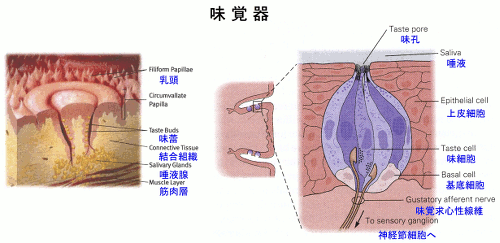
刺激の変換(塩味と酸味/イオン・チャネル型受容体)
味蕾は舌全体に2,000〜5,000ぐらいあるのだが、味蕾の一つ一つの中に味細胞が集団で存在する。味細胞の中に、塩味、酸味等の5成分に反応する機能蛋白がそれぞれある。
[図2]は、味細胞の反応を電気生理学的に測定したものであり、どの細胞が何によってよく反応するかを示している。
塩味に反応する細胞1では、味蕾の細胞に塩分を含んだ溶液が流れてくると、Na+がNa+イオン・チャネルを通って味細胞内に入る。すると味細胞が活性化され、その情報が神経節細胞へ伝えられて、脳に伝えられる。
酸味に反応する細胞2では、酸味物質に含まれるH+イオンが味細胞に到達すると、それがH+イオン・チャネルを通って、細胞内に流入する。これにより味細胞が活性化される。H+イオンは、またK+イオンチャンネルを閉じ、細胞内から細胞外へのK+イオンの流出を止める(細胞内はK+の濃度が非常に高く、K+の外への流出が抑えられると、細胞が興奮する)。このように酸味については2つのチャネルが関わっている。
刺激の変換(甘味・苦味・旨味/Gタンパク質共役受容体)
甘味の場合は、イオンが流れるのではなく、糖の分子が細胞膜の受容体に結合して受容体を活性化することにより、情報が神経細胞に伝えられる。
旨味の場合は、アミノ酸に受容体が反応して情報が伝わる。マウスの受容体はさまざまなアミノ酸に同程度に反応するが、人間は受容体の構造が少し違い、アミノ酸の中でもグルタミン酸に対して特に反応性が高いため、グルタミン酸に特に旨味を感じる。
[図4]の下から2つめが甘味受容体を、一番下が旨味受容体を指している。
図の上の2列は苦味である。受容体のくぼんだところに苦味物質が結合して、味細胞が反応し、その情報が神経細胞に伝えられる。苦味受容体遺伝子は20種類から30種類あることが知られている。苦いものは、食べると下痢を起こしたり、あるいは死に至る、という危険な物質を多く含む。したがって動物は、苦味系統の受容体を増やすことによって、危険な物質を感知する範囲を広げ、苦いと感じれば吐き出すことで生き延びてきた。苦味は味の一要素であるが、一方では危険物質への警鐘でもあるのだ。また、苦味の受容体の構造が人によって少しずつ異なるため、苦味の感じ方は人によって違う。ある人にとっては非常に苦く感じるが、別の人にはそれほど感じないといったことも起きる。
このように、味物質に対し反応する機能蛋白がそれぞれ存在するがゆえに、5種類の味を感じ分けることができるのである。
図2・3 刺激の変換(塩味・酸味) 図4 刺激の変換(苦味・甘味・旨味)
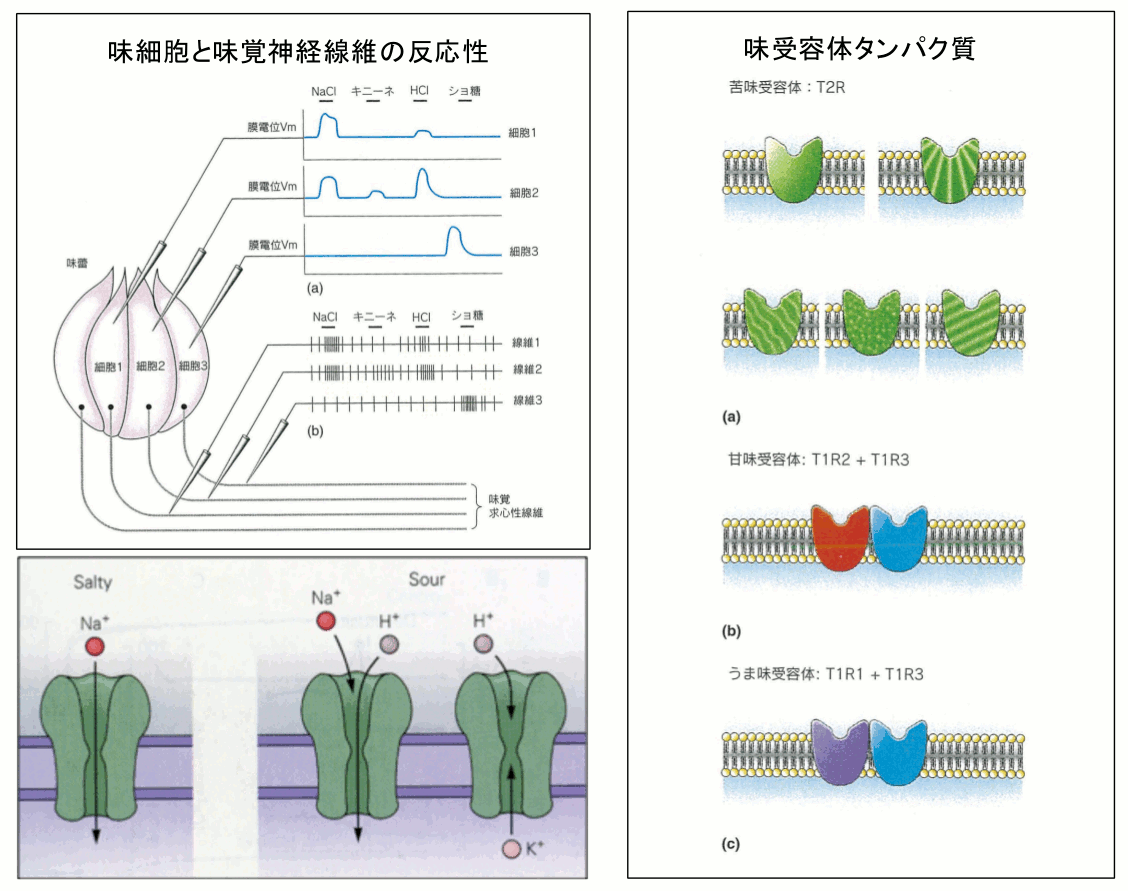
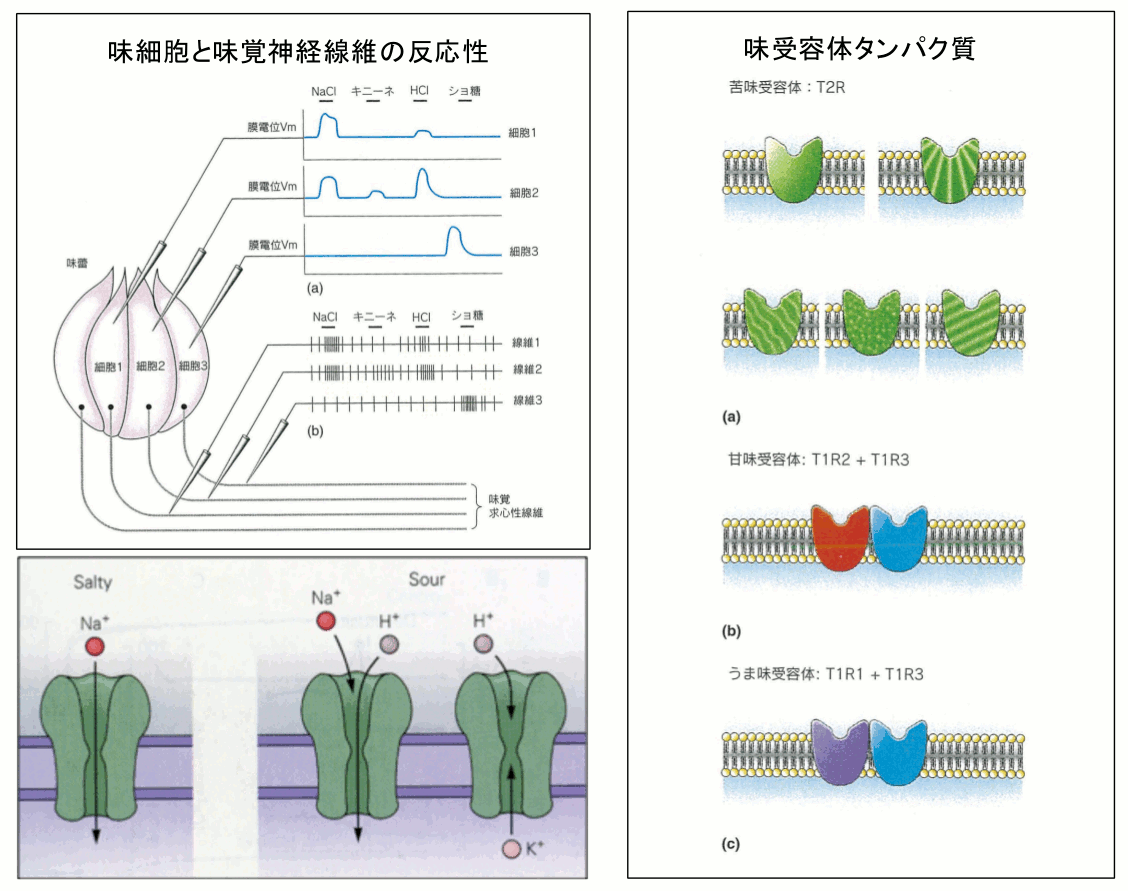
神経節細胞
味情報は、舌にある味細胞から3つの神経によって脳へ伝達される。舌の前2/3の部分は顔面神経(第7脳神経)が支配し、舌の後ろ1/3の部分は舌咽神経(第9脳神経)が支配している。喉頭、咽頭は迷走神経(第10脳神経)が支配している(喉頭、咽頭も味を感じる能力を持っている)。この3つの神経が束になり、延髄にある味覚核に収斂する。そこから次の神経核(視床)に伝わり、さらに脳(大脳皮質)の一次味覚野に伝わる。これが味覚の伝達経路である。視床は、視覚系、触覚系などさまざまな一連の神経が集まるところであり、単に味覚だけでなく、においや舌触り、見た感じを含めて認識する。同じ甘味でも、ブドウ糖とアイスクリームではおいしさの感覚が違うのはこのためである。
以上のように、最初に舌で処理された情報が、脳神経のネットワークの中で統合され、脳(大脳皮質)において独特の味として認識される。
神経伝達物質の一つ、ドーパミン
それでは、今日の命題である、何かを「好む」「求める」というのはどの程度分かってきたのだろうか。
現在の脳科学の多くはモデル動物を使って行う。仮にその動物が「何かを好んでいる」という行動を示しても動物の好みを科学的に解析するのは難しく、人間の場合に敷衍して、どういうメカニズムで起こるのかを解明することも非常に難しい。一方、「求める」のほうは、求めているか否かを行動科学的に解析することが比較的簡単であり、その理解が大きく進んだ。
「求める」という働きには、ドーパミンという神経伝達物質を産生している「黒質」及び「腹側被蓋野」(中脳の一部)という2つの脳部位が関わっている。神経伝達物質とは、神経細胞間で情報をやりとりするために必要な物質であり、前の神経細胞から分泌され次の神経細胞を興奮あるいは抑制することによって神経情報を伝える。50種類以上の神経伝達物質が確認されており、興奮性のものとしてはグルタミン酸がある。抑制性の神経伝達物質にはGABA(γ-アミノ酪酸)があり、情動(感情)・報酬などに関係する神経伝達物質にはドーパミンやセロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン等がある。
さて、何かを求めようとする時にはドーパミンが分泌される(快感神経系のスイッチを入れるのがドーパミンである)。「黒質」「腹側被蓋野」で作られたドーパミンは神経繊維によって運ばれ「線条体」や「前頭葉」で作用する。
線条体は、生存に必須の情報処理と統合を行う神経系の中でも重要なところであり、下等な生物から我々ヒトに至るまで存在する最も基本的な脳部位の一つである。前頭葉は短期記憶などをつかさどる部位であり、この機能が落ちてくると老人性の機能低下が起こるので注意すべき場所だ。
大脳基底核が「報酬」と「忌避」を支配する
今述べた「黒質」および「線条体」は、大脳基底核に属する。大脳基底核の機能は大きく二つある。
最もよく知られているのが、運動の記憶及び運動のバランス制御である。話はややそれるが、運動の記憶は、他の部位、例えば小脳も担っている。テニスがだんだんうまくなる、スキーがだんだん上達する、というのは小脳で運動の情報がうまく蓄積されるからであり、これを運動記憶という。運動のバランスは大脳基底核で制御されている。この大脳基底核の疾患で代表的なものがパーキンソン病であり、運動のバランスがうまく制御できないために姿勢の保持が困難になる、動作が緩慢になる、手指が震えるといった症状が出る。「黒質」や「腹側被蓋野」でドーパミンを作る細胞が死んでしまうため(原因は不明)、ドーパミンが減り、運動障害が起きるというわけである。
話を元にもどすと、大脳基底核のもう一つの重要な役割が、「報酬系」と「忌避系」の支配である。報酬系とは、何か好ましい物があることが分かった時やそれが期待できる時に活性化され、快の感覚を与える神経系である。
「あの場所にチョコレートがある」という報酬刺激があってそれを獲得した時や獲得することが期待できる時、黒質(緻密部という部位)にあるドーパミン神経細胞が興奮して、ドーパミン分泌を引き起こす。一方、「求めよう」という欲求は大脳皮質から線条体に情報がきて、ドーパミンの作用も働いて大脳皮質から線条体さらに黒質(網様部という部位)へ情報が伝わるという具合である。
さらに線条体には、興奮させる経路(直接路といい、報酬に強く関わる)に加えて、抑制させる経路(間接路といい、忌避に強く関わる)があり、二つがうまく働くことにより何かを求め何かを避けるという制御がなされている。この報酬と忌避記憶が2つの経路によって制御されているというのは我々の研究によってここ数年で明らかになった点である。
薬物依存症はドーパミンの異常による
ここでコカインなど薬物依存症の問題に触れておこう。自然の報酬の場合、報酬刺激のある時だけドーパミンの濃度が上がるが、コカインなど依存性薬物はドーパミンを作る細胞を興奮させ続け、ドーパミンを持続的に高めてしまうのである。薬物依存を起こす物質はどこに作用するのか。さまざまな研究の結果、15〜20年前に、ヘロインやニコチンは「黒質」や「腹側被蓋野」に主に働き、コカインは情報の投射先である「線条体」(の側坐核という部位)で働くこと、即ち報酬系の回路が活性化されること、そして、薬物依存症を引き起こすのは、ドーパミン濃度の上昇異常により神経回路の情報処理が狂うことが原因であるということが明らかになった。
通常、ドーパミンは刺激のある時に分泌されて作用し、そのあとは必ず再吸収されるため、永続的に線条体を興奮させ続けることはない。一方、コカインはドーパミンの再吸収を抑えて線条体を興奮させ続けること、即ち再吸収されるはずのドーパミンをブロックして、線条体のドーパミン濃度を上げたままにしてしまう結果であることがわかってきた。
ドーパミン濃度が高いままだとなぜその物質を求め続けるのか、といった薬物依存の研究が現在精力的に進められているが、分からないことはまだまだ多い。
報酬反応・忌避反応のメカニズム(受容体)
先に述べたように、線条体には、興奮に関わる直接路と抑制に関わる間接路がある。直接路は、線条体→淡蒼球内節・黒質網様部からなっており、一方、間接路は、線条体→淡蒼球外節・視床下核→淡蒼球内節・黒質網様部からなる。線条体でドーパミンに反応する受容体はD1、D2の2つがあり、興奮(活動)させる受容体D1は直接路に、抑制系の受容体D2は間接路に、特異的に存在する。
D1はドーパミン濃度が相当に高まってはじめて反応するのに対して、D2は非常に低い濃度でも反応する(反応性が高い)。つまり通常は、受容体D2は効いているが、D1は効いていない。報酬刺激があると、ドーパミン濃度がどっと上がり、D1が活性化されて直接路が働くようになり、報酬を求めようという反応になる。一方、嫌悪刺激があるとドーパミン濃度は下がり、D2はドーパミンによる抑制を解除し、抑制系のD2が反応しなくなり、今まで抑制されていた間接路が働くようになる。その結果、大脳皮質からの入力が働いて、忌避反応を起こす(直接路はもともと反応性が低いので、ドーパミン濃度が下がっても関係がない)。つまり、D1とD2の働きが異なり、分布も違うことによって、報酬刺激と忌避刺激によっておこるドーパミン濃度の上がり下がりの情報が直接路と間接路でうまく振り分けられて、報酬反応、忌避反応が起こるのである。
記憶を使った報酬予測
いま何が好ましい物(たとえばチョコレート)がある場所にあるとする。しかしそこにあるのは偶然である可能性もある。ただし、そこにいつもチョコレートがある場合には、そのたびに直接路が興奮するため、その情報が蓄積され報酬記憶が誘導される。動物は、エサは偶然にあったのではない、あの場所にはきっとあるだろう、という予測を立て効率的に報酬を得ることができるようになる。
一方、嫌悪刺激は、仮にそれが偶然であってもそこへは二度と行かないほうがより安全であり、ドーパミンの低下による忌避記憶を瞬時に獲得し、その記憶をとにかく残しておく。
何かを求めたり、避けたりという行動は、生存にとって不可欠である。例えば、エサが充分にあるが、危険が伴う場所にある場合と、エサは少ないが危険は全くないという場合がある時、動物はどちらを選択するだろうか。動物がどれだけおなかが減っているかなど、その時どきの状況によって違ってくるだろう。いずれにしても動物は報酬と忌避を選択しなければならない。それが基底核という脳部位で、ドーパミンの上がり下がりによってうまく決定されるのだ。
コカインなどの薬物は、長期にわたって線条体のドーパミン濃度を上げるため、実際にはコカインを摂取すると身体の障害が起こってきて決して「好み」ではなくなってくるが、異常に「求める」という脳機能が働く。報酬記憶が異常に残ってしまうがゆえに、精神依存を作り出し、やめたくてもやめられなくなる。薬物依存症は報酬系の異常さが情報として固定されることによって起こるものであるが、脳機能自体としては生理学的な反応が働いているとも言える。
習慣化
脳は、すべての情報に対して常にその都度処理するのでなく、次第に状況に応じて行動することができるようになる。あることがうまくいくと、その刺激がちょっと入るだけで、あえて神経を興奮させなくてもできるような「習慣化」が起こる。これも脳の特徴である。逆に、この「習慣化」によって即座に反応できず、過ちを犯すことが多分にある。
右側にエサを置いた時、エサを求めているマウスは、周りの景色を見て次第に右側にエサがあることを知り、右に曲がる。はじめのうちは周りの状況を見て右に曲がり、エサに到達する。この訓練を充分に繰り返すと、マウスは周りの景色を見ずに無意識に右に曲がる。「景色によって」覚え、次に「右に曲がれば」エサがあると2段階の覚え方をするから、充分に記憶してしまうと動作だけを覚える。この時にマウスを逆サイドに置くと、エサのない向かって右方向に曲がってしまうのである。
こういった「習慣化」は我々の生活でもごく一般的に起きることである。会社帰りに奥さんからスーパーマーケットでの買い物を頼まれた時に、途中で曲がらなければならないのに、つい普段どおりの道を行ってしまうのだ。
我々の脳は、特別のことが起こらない普段は「習慣化」によって正しい行動を起こすことができ、何か新たな情報が入ってきた時にはちゃんと反応するようにできている。しかし、あるものを「好む」「求める」といった無意識の意思決定の習慣化が、どういうメカニズムで起こるのか──例えば「母親の味」がどういうメカニズムなのかは、まだまだ分かっていない。
母親の味噌汁の味というのは子どもの頃の情報だから、DNAの遺伝情報に元々あるものでない。DNAの塩基配列の違いによらない、環境によってもたらされる遺伝子発現の多様性を生み出すしくみ、即ちエピジェネティックと呼ばれるしくみによって起こると考えられており、現在精力的に研究が進められている。味覚、嗅覚、視覚、知覚などによる好み、即ち嗜好は、脳が外界からの情報をどのように処理し、統合して生じるのか、高次な脳機能を理解する上で極めて興味ある問題として現在精力的な研究が進められている。
脳機能のさらなる解明に向けて
「求める」ことについては、報酬・忌避、習慣化といった機能を通じて、線条体、黒質、大脳皮質が中心的な役割を果たしていることが明らかにされてきた。ただし、あることを求めるか求めないかは決して単純な制御ではなく、それまでの経験や、その時の飢餓状態や、どれだけ精神状態が高揚しているか、あるいは何らかの不安があるかといった、その時に置かれた状況が脳に情報として働くのであって、それらについては違う脳部位が働いている。例えば「情動」「恐れ」「恐怖」の場合は扁桃体という部位であり、「不安」は中隔核という部位である。
「不安」と一言で言っても、高いところに行った時不安なのは人間もマウスも同じだが、明日試験があるから不安だ、ということはマウスにはないだろう。同様に、一見単純に思われる報酬・忌避も周りの状況に影響される。したがって、感覚系とそれを支配する脳機能、あるいはほかの脳機能が相互にどのように関係し合って、一連の高次な脳機能が起こるのか、という研究が進められている。
さらに言えば個性の問題も加わる。その人が本来意欲的であるか、注意力散漫であるか、といったことである。先の例で言えば、危険でも報酬を求めるかどうかは、どれだけおなかがすいているかにもよるが、性格的に失敗を恐れない人は大きな報酬のほうを求めるだろうし、それが異常であるとギャンブル症が起きる。個性の問題を理解するために例えばドーパミンの受容体の遺伝子変異と性格が対応するのかどうかといったパーソナリティの問題についても、現在解析が進みつつある。
嗜好の中の「求める」という問題は、我々の社会生活と非常に関係が深い。今はそれを解析できる時代にもなってきた。ならば、「好む」ということがなぜ起きるのか、その理解の道のりはなかなか遠いが、脳科学の進歩によって次第に分かってくるものと思う。
「謝辞」
図の一部は下記の文献から引用し改変した。
1. Principles of Neural Science (E.R.Kandel他、McGraw-Hill, 4th edition)
2. 神経科学(ベアー、コノーズ、パラディーン:加藤宏司、後藤薫、藤井聡、山崎良彦 監訳、西村書店)
(平成24年8月12日)