 |
|
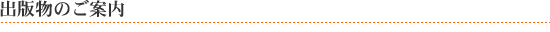
| 嗜好品文化研究会では、この分野に興味を持つ人が増え、この分野の研究や議論がさらに進むことを期待して、研究成果を適宜とりまとめ、出版しています。 |
|
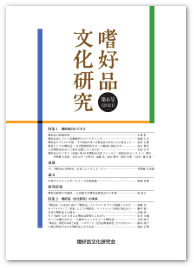
|
2021年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第6号(2021)
深淵なる疑問 “嗜好品とは一体何なのか” を多くの人たちと共有し、面白い論点を提示していこうと考え、2016年より研究誌(年刊)を公刊しました。第6号(2021年発行)をもって休刊となりますが、これまでご執筆・ご愛読いただいた皆様に心からの感謝を申し上げます。
入手を希望される方は、郵便振替をご利用ください。
加入者名:嗜好品文化研究会
振替口座番号:00980-1-309629
なお、「雑誌──嗜好品文化研究 第〇号 頒布希望」としてご住所・お名前をご連絡いただければ、手数料当方負担の振替用紙をお送りいたします。
email:minowa★cdij.org(★を半角@にしてください)
〈目次〉
特集1 嗜好品のビジネス
嗜好品の拡張世界 小林 哲
嗜好品化していく炭酸飲料とマーケティング 赤岡 仁之
嗜好品ビジネスの今後 ─その原料の多くが農産品であることに着目して 疋田 正博
抵抗としての嗜好品 ─なぜ精神科医がビール醸造に挑むのか 高木 俊介
人は嗜好品を介して何を交換しているのか 太田 心平
嗜好品のビジネス[討論] 第18回嗜好品文化フォーラム(オンライン)報告
連載
今、「嗜好品の世界史」を書くということ(下) 井野瀬 久美恵
論文
中世のイエメンとギーとインド洋西海域 馬場 多聞
研究情報
嗜好品研究の可能性 ─立命館大学嗜好品研究会の3年間 南 直人
特集2 嗜好品(文化研究)の未来
「嗜好品」の未来に向け「嗜好品」というコンセプトと格闘してみた 斎藤 光
モバイルメディア「原基」としての嗜好品 ─イノベーション研究の視点から 藤本 憲一
未来の嗜好品とは何か 山極 壽一
モノ・場所・人から考える嗜好品研究のこれから 安井 大輔
カートを噛みながら ─人類学とインタビューと嗜好品 大坪 玲子
「嗜好品」研究の来歴と命運 ─バルザック『近代的興奮剤考』をてがかりに 橋本 周子
人類文明史のなかの嗜好品とその未来 髙田 公理
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2021年3月31日
183p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|

|
2020年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第5号(2020)
〈目次〉
特集 嗜好品とAI
AIは〈味覚/趣味〉変容の精妙さを思考しうるか ─E・バーク美学で読む人間的成熟と崇高な嗜好 桑島 秀樹
味と匂いの可視化にAIは使えるか 都甲 潔
AI社会での愉しみ方 江間 有沙
AIと嗜好品をめぐって 髙田 公理
嗜好品とAI[討論] 第17回嗜好品文化フォーラム報告
連載
今、「嗜好品の世界史」を書くということ(上) 井野瀬 久美恵
論文
文人雅遊と煎茶書 ─『青湾茶話』を中心に 梁 旭璋
ロシアの茶の歴史と現在の喫茶事情 廣部 綾乃
嗜好品からドラッグへ ─イギリス・オランダのイエメン人とカート 大坪 玲子
日本のシガレットのパッケージデザインの特徴とは 山本 拓哉
表出する情動,試論 ─音楽と「建てること」をめぐって 田中 理恵子
書評
「小確幸」文学から、「食の起源」まで 藤本 憲一
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2020年3月31日
122p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|

|
2019年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第4号(2019)
〈目次〉
特集 嗜好品とデザイン
現代社会における嗜好品のデザイン 高安 啓介
嗜好品、それは価値判断の基準 柏木 博
香りのデザイン 鈴木 隆
Re; 物事見直しの時代に 小池 一子
「酒飯論絵巻」の引用をめぐる考察 ─風俗画の誕生─ 並木 誠士
たばこパッケージにみるデザインのチカラ 半田 昌之
パイプのデザイン 青羽 芳裕
アメリカの家庭用コーヒー・メーカー ─その発展・普及とデザインの変遷─ 面矢 慎介
嗜好品としてのクルマのデザイン 龍造寺 邦昭
いまデザインとは ─KYOTO Design Labの試み─ 小野 芳朗
嗜好品をデザインする 井野瀬 久美惠
嗜好品とデザイン[討論] 第16回嗜好品文化フォーラム報告
論文
目で味わうことの心理学 大沼 卓也
インドネシア・スンダ農村における食行動の動機 小坂 理子
研究情報
嗜好品研究の最前線 大坪 玲子
書評
交差する嗜好品 ─文化と偶然性─ 斎藤 光
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2019年3月31日
153p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|
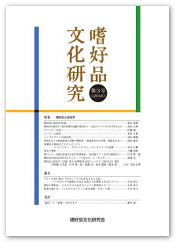
|
平成30年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第3号(2018)
〈目次〉
特集 嗜好品と政治学
嗜好品の政治学序説 新川 達郎
嗜好品の政治学:酒と飲酒の忌避の歴史から──近代のアメリカと日本を中心に 髙田 公理
タバコと「空気」 伊藤 陽一
コーヒーと政治 疋田 正博
シンプルライフの政治性 速水 健朗
食料をめぐる経済政策と消費の嗜好性──戦前期日本の米穀・食塩を中心に 前田 廉孝
食嗜好と移民のアイデンティティ──エスニシティ・グローバリティ・ローカリティの交錯 安井 大輔
外交と嗜好 八幡 和郎
朝コーヒーを飲む普通の生活の世界政治──20世紀ドイツ文学の視座から 臼井 隆一郎
嗜好品が政治を帯びるところ──「つながり」と「からだ」 斎藤 光
嗜好品と政治学[討論] 第15回嗜好品文化フォーラム報告
論文
ワインの回し飲み「ポロン」でつながるひとと文化──バルセロナの調査から見える暮らしの嗜好と社会について 中村 設子
移民と嗜好品──エチオピアにおけるイエメン系移民とカート 大坪 玲子
給食の愉しみ ──「こんだてひょう」に見る果物・デザート類 小川 聖子
書評
「猫舌」と「食通」のはざまで 藤本 憲一
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2018年3月31日
158p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|
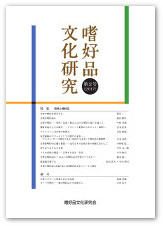
|
平成29年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第2号(2017)
〈目次〉
特集 音楽と嗜好品
音楽の嗜好を科学する 福井 一
音楽は嗜好品か 岡田 暁生
音楽の嗜好 ──時代・民族・個人における嗜好の違いを通して 中村 孝義
嗜好対象としての歌声 ──クラシック歌唱からポピュラー歌唱へ 宮本 直美
アレンジャーは音楽の料理人 吉村 晴哉
近代経験のアリーナとしての歌手の身体──チベタン・ポップ制作に見る「屈折する近代」と嗜好品の動態性 山本 達也
音楽的嗜好の伝播と横領──近代日本の民衆音楽の経験に注目して 小野塚 知二
香りがつなぐ人と音楽 平井 丈二郎
ノリの意味と構造──音楽する社会・再考 小川 博司
音楽は嗜好品か? あるいは嗜好品は音楽たりうるか? 藤本 憲一
歌謡曲を愛でる 近田 春夫×小川 博司
音楽と嗜好品[討論] 第14回嗜好品文化フォーラム報告
論文
中世イスラーム世界における乳香 馬場 多聞
カートを嗜む──他の嗜好品との比較から 大坪 玲子
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2017年3月31日
129p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|

|
平成28年度発行
研究誌『嗜好品文化研究』第1号(2016)
〈目次〉
特集 嗜好品と香り
嗜好品と香り/嗜好品の香り 鈴木隆
「香水男子」をめぐって 斎藤光
香りを食べる 山崎寿美子
アートとしての香り 岩﨑陽子
匂いについての考察 栗田靖之
ワインのテイスティングとは 佐藤陽一
嗜好品と香り[討論] 第13回嗜好品文化フォーラム報告
論文
啓蒙の飲料 橋本周子
ブンとギシュル 大坪玲子
トリーノとジャンドゥイオット 中島梓
妊婦にとって〈嗜好品〉とは何か 大淵裕美
研究ノート ランク付けされる「食」 中田梓音
研究ノート 北インド、ヒンドゥー既婚女性の装いとその嗜好の背景 岡田朋子
研究ノート 子ども向け化粧品とマンガ 小出治都子
書評
10冊の本から見える、嗜好品世界の広がり 藤本憲一
編集・発行:嗜好品文化研究会
発行:2016年3月31日
137p,30cm
頒価:1,000円(送料当方負担)
ISSN:2432-0862
|

|
平成19年度発行
『嗜好品文化を学ぶ人のために』
嗜好品文化研究は、これまで学問として確立されていない分野ですが、人間が生きていくうえでさまざまな楽しみを生んできた「嗜好品」というものの奥深さとおもしろさを解き明かし、嗜好品文化研究の意義と問題発見の糸口をわかりやすく紹介する書籍です。さまざまな専門的見地から嗜好品や嗜好品的なものの研究に取り組んでいる研究者が、さまざまな問題提起とアプローチの方法があることを解説し、初学者から異分野の研究者まで幅広く使っていただけるものになりました。嗜好品文化研究会・研究奨励事業(研究助成)のガイド・ブックとしてご利用ください。
〈目次〉
序章 嗜好品文化研究への招待
第1章 多様なる嗜好品の世界
コーヒー
茶・紅茶
酒・アルコール飲料
たばこ
清涼飲料水
カカオ・チョコレート
菓子
香辛料
ビンロウ
コーラ
カヴァ
カート
第2章 広がりゆく嗜好品の世界
ハチミツ
砂糖
香水
お香
油脂
水
塩
音楽
ケータイ
第3章 嗜好品文化へのアプローチ
歴史学
文化人類学
経済学・経営学
法学・政治学
社会学
宗教学
文学
心理学
生理学
植物学
第4章 嗜好品文化研究の古典紹介
臼井隆一郎『コーヒーが廻り世界史が廻る』
小林章夫『コーヒー・ハウス』
広瀬幸雄・星田宏司『増補・コーヒー学講義』
岡倉天心『茶の本』
谷晃『わかりやすい茶の湯の文化』
角山榮『茶の世界史』
麻井宇介『比較ワイン文化考』
石毛直道編『論集 酒と飲酒の文化』
坂口謹一郎『日本の酒』
米山俊直・吉田集而ほか編『アベセデス・マトリクス』
上野堅實『タバコの歴史』
グッドマン『タバコの世界史』
ペンダグラスト『コカ・コーラ帝国の興亡』
ウォーバートン&シャーウッド編『ストレスと快楽』
コルバン『においの歴史』
シヴェルブシュ『楽園・味覚・理性』
ドッジ『世界を変えた植物』
松浦いね・たばこ総合センター編『世界嗜好品百科』
ワインバーグ&ビーラー『カフェイン全書』
終章 嗜好品文化研究の発展のために
著者:高田公理+嗜好品文化研究会
発行:世界思想社
発売:2008年4月30日
252p,19cm
定価:2,000円+税
ISBN:978-4-7907-1329-6
|
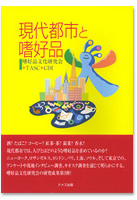
|
平成15年度研究成果
『現代都市と嗜好品』
平成15年度(研究会3年目)は、初年度の現代日本の嗜好品、2年目の諸民族の嗜好品の研究をふまえ、「現代世界の都市社会における嗜好品」をテーマとして、諸都市の嗜好品とそのイメージについての比較を、アンケートとインタビュー調査、キオスクの実態調査を通して行いました。調査対象は、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリ、上海、ソウル、東京です。この調査の成果を、研究会関係者だけで利用するのではなく、この分野に興味を持つ人が増え、この分野の研究や議論がさらに進むことを期待して、基礎的データを含めて公刊しました。各都市のこれからの嗜好品のありかたを占い、日本の嗜好品の未来についても予測する、新しいジャンルの本書をどうぞご覧ください。
〈目次〉
第1部 7つの都市の嗜好品
1 多忙なニューヨーカーの嗜好品
2 コーラ1本でも車で買いに行くロサンゼルス
3 イメージを裏切ったロンドン
4 時間をかけて嗜好品をたのしむパリ
5 医食同源にこだわる上海
6 嗜好品が社交に役立つソウル
7 嗜好品を気軽に持ち歩くまち東京
8 嗜好品による都市比較
第2部 都市の駅で見た嗜好品
1 各都市のKIOSK調査
2 KIOSK調査からみえるもの
第3部 都市社会のおもな嗜好品
1 酒──酩酊に不寛容な現代都市
2 タバコ──健康志向と嗜みの文化
3 コーヒー──変身しつつ定着する不思議な液体
4 紅茶・茶──紡ぎ出されるプラスイメージ
5 清涼飲料水・水──ただの水から刺激のあるものまで
6 菓子──おやつからデザートまで
7 香水──身に纏う嗜好品
8 現代都市社会の嗜好品
資料編
著者:嗜好品文化研究会+TASC(たばこ総合研究センター)+CDI
発行:ドメス出版
発売:2005年2月28日
270p,26cm
定価:5,000円+税
ISBN:4-8107-0635-4 |
 |
平成14年度研究成果
『嗜好品の文化人類学』
平成14年度は、嗜好品文化研究会2年目の年。研究会では、生活様式が異なる世界の諸民族が、栄養摂取だけではなく嗜好品をたしなみ、また重要なものとして扱っていることに注目し、「諸民族文化のなかの嗜好品」をテーマに、世界各地で精力的にフィールド調査を展開しておられる21人の先生方からお話を聴きました。さまざまな民族で、コーヒー、酒、タバコののみ方さえ、日本と必ずしも同じでないことがわかり、日本ではあまり知られていない、変わった木の実や葉っぱ、木の芽などを噛んだりする習慣もたくさんあり、時間をかけてゆっくりと楽しまれていることもわかりました。こういった1年間の研究成果をコンパクトに編集したのが本書です。
〈目次〉
序章 嗜好品に関する文化人類学的考察
第1章 嗜好品世界の普遍性と特殊性
韓国における嗜好品──儒教は何をもたらしたか
酔わないイタリア、酔うギリシア
タイのコーヒー、ラオスのコーヒー──嗜好品と生活スタイル
天と人、人と人をつなぐモンゴル人の嗜好品的世界
第2章 現代世界に広がった嗜好品のふるさと
世界に根づいたメソアメリカの嗜好品──酒・タバコからトウガラシまで
ブラジルの国民的な飲み物=ガラナ
大昔からコカの葉を噛みつづけてきたアンデスの人びと
第3章 豊饒で華麗な嗜好品的世界を持つ社会
インド・ベンガルの嗜好品──酒に厳しく、大麻に寛容な社会
西アフリカ・カメルーンにおける嗜好品──コーラを噛む人びと
嗜好品とともに過ぎ行くエチオピア高地の一日
中国人の三大嗜好品──嗜好・養生・社会性
第4章 ビンロウ、カート、そしてカヴァ
社交の道具としてのカート──イエメンの嗜好品
台湾の嗜好品──酒・タバコ・ビンロウ
ビンロウがなくなると暴動が起こる?──酒のなかったパプアニューギニアの今日
カヴァからサモアが見える
第5章 意外なモノが嗜好品になる社会
コンゴ民主共和国ピグミーの嗜好品──ハチミツをむさぼり、ゾウの脂を味わう
マダガスカルの嗜好品──「祝祭」としてのウミガメ食
ネパール・マガール人の〈嗜好品的なるもの〉
パキスタンの嗜好品とイスラーム的慈善制度
シベリア、アムール川流域先住民の嗜好品──中国とロシアのあいだで
胆汁の苦味と糞便臭を楽しむ
終章 嗜好品の比較文化
著者:高田公理+栗田靖之+CDI
発行:講談社・選書メチエ296
発売:2004年4月10日
264p,19cm.
定価:1,700円+税
ISBN:4-06-258296-1 |
 |
平成13年度研究成果
『なぜ「ただの水」が売れるのか 〜嗜好品の文化論』
平成13年度は、嗜好品文化研究会が正式に発足した年です。研究会では、「現代日本における嗜好品」をテーマに、まずわれわれの暮らす現代の日本において、嗜好品がどのような位置づけにおいて人々にとらえられているのか、調査研究をおこないました。その結果を研究会代表幹事である高田公理がまとめたのが、この本です。
関東・関西でのさまざまな世代へのグループインタビュー調査、2,000人規模の意識調査、これらをもとにした研究会での議論とゲストスピーカーによる報告、そして第1回嗜好品文化フォーラムのパネルディスカッションで展開された議論などが、さまざまな形で織り込まれています。嗜好品文化研究の多彩な広がりを実感してください。
〈目次〉
第1章 嗜好品が開く「楽しみの時代」
第2章 「楽しむ」という価値の発見に向けて
1 「はたちの女子学生」たちの嗜好品世界
2 「天下とっても二合半」──高齢男性の嗜好品世界
3 「嗜好品ルネッサンス」が開く「楽しみの時代」
第3章 現代日本人の楽しみと嗜好品
1 嗜好品は「心の栄養」──首都圏の独身OL
2 「好きなもの」は海外旅行に持っていく──関西の独身OL
3 「趣味と嗜好品」を分けるのは難しい──関西の独身サラリーマン
4 「おみやげ」になれば食べ物も嗜好品──関西の子育て一段落ママ
5 嗜好品は時代とともに変化する──首都圏中高年サラリーマン
6 香りの強い「旬の食べもの」への関心──関西の六、七十代・熟年女性
7 味覚や嗅覚の刺激でさまざまな「気分転換」──大量アンケート調査の結果から
第4章 嗜好品としての清涼飲料水とその市場
1 マーケティング研究に「嗜好品」を位置づける
2 清涼飲料水は「嗜好品」の一種である
3 嗜好品としての清涼飲料水の特徴はさまざま
4 マーケティング研究から見た嗜好品市場
第5章 嗜好品世界の広がりと多様性
1 植物を噛む──「チューイング」型の嗜好品
2 チューイングからドリンキングへ
3 幻覚剤とそれから派生した酒という飲料
4 その他、さまざまな嗜好品の源流
5 「嗜好品」というカテゴリーを拡張する
6 よみがえるか?「たしなみ」の文化
第6章 情報社会で嗜好品が果たす役割
1 現代の「情報社会」について考える
2 嗜好品を用いて「自分以外の存在になりたい」
3 近代的な市民社会の成立と嗜好品の役割
4 嗜好品に映し出される時代精神
終章 「相互ケアの時代」と嗜好品
付録──研究会メンバーの「嗜好品文化研究」への思い
筆者:高田公理
発行:PHP研究所
発売:2004年1月5日
300p,19cm
定価:1,400円+税
ISBN:4-569-63358-7 |
|
 |
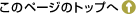 |
 |
|
